
こんにちは
マナビツナグヒトのみこりんです。
5月も半ばを過ぎました。
今週・来週末は、春の運動会が行われる学校が多いと思います。
校外学習も始まる頃です。
新しい学年・学級にも慣れ、
子どもも大人もだんだんとわがままが出てくるのがこの時期です。
今日は、登校しぶりについて書きます。
5月の連休明けまでの登校しぶりは、
学校生活に慣れないことからくる不安が多いです。
4月は新たな環境に適応しようとして、一生懸命がんばるのですが、
その疲れが連休明けにドドッと出てくるというところです。
しかし、今の時期まで続いているとしたらお母さんもお父さんも心配ですよね。
登校しぶりの原因は大きく分けて3つあります。
児童期は、身体が大きく成長する時期です。
学校でも家庭でも元気いっぱい、活動的に日中を過ごすことで、
身体機能を高めていく時期でもあります。
だからこそ、栄養のバランスがとれた食事と十分な休養が必要です。
それらを心がけていると自然とメリハリのある生活を送ることになります。
登校時にぐずるお子さん(特に低学年)の中には、
毎朝のスタートが気持ちよく切れないことが原因になっている場合もあります。
そのためにも、夜早く寝ることで朝起きをスムーズにする生活リズムを
整えることが大切です。

子どもにも得手不得手はあります。
不得手な物事に関しては、ついつい腰が引けてしまうこと、
大人にだってあると思います。
そういう時は、あまり無理せずできる範囲でよしとするとか、
違う人に手伝ってもらうとか、
そもそも不要であれば排除してしまうとか、
大人であれば、色々考えて乗り越えると思います。
でも、子どもの中には、そのことを無意識で捉えている場合が多いです。
なんとなく、モヤモヤする。
その心の奥底に、不得手なものや避けたいものが鎮座ましていることも少なくありません。
“給食を全部食べられない”、“絵を描くのがいや”、“近くの席の友達が気になる”、
そんな些細なことが・・・というものこそが、登校時に心の中をざわつかせる犯人
という場合もよくあることなのです。
そういう場合は、それの対処法を決めるか思いきって排除してしまうのが一番です。
その不安がなくなったことで、人が変わったように学校に行き始めるお子さんも多いですよ。

上記の2つの場合は、原因がはっきりしてるので、
それに対する適切な対応をすれば、解決に向かいます。
これといった原因がなく、解決の手だても見つからず、とにかく長引くもの。
そういう場合は、お子さん本人が持っている特性による場合があります。
発達障害は既に認知も進み、
個の特性にあった接し方や対応を行うことで困り感を軽減しています。
最近「ひといちばい感じやすい子」という特性も耳にすることが多くなりました。
私は、これは友人から聞くまでは認識したことがなかったので、
そういう子への適切な対応ができていなかったと反省しました。
心理学者アーロン博士が、提示した「ハイリーセンシティブチャイルド」は、
“過敏に反応しやすい”,“共感性が高い”,“わずかな違いや変化にも気がつく”、などの特性を有しています。
全体の15~20%に上るお子さんが、多少なりともその傾向があるということなので、
そういう場合もあるかと思います。
この3に当てはまるお子さんならば、素人診断で判断せずに、
専門家に相談することが必要です。
どういう状況が、そのお子さんに合うかを知り対応することが望ましいと思います。

3つの原因をあげました。
共通点はわかりますか?
それは、お子さんの様子をよく観察したり話を聴いたりすることが、
原因を知ることにつながるということです。
中には、めんどくさい~と「学校行きたくない」をいう時もあるでしょう。
でも、それはよく観察しコミュニケーションをとっていれば、
気づくことができます。
こういう現象に慌ててしまいがちですが、そういう時こそ目と耳と心を働かせ、
お子さんの様子を把握する機会としてはいかがでしょう。
読んでくださりありがとうございました。
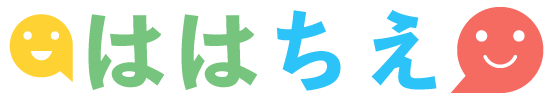
Facebookコメント